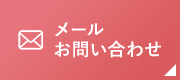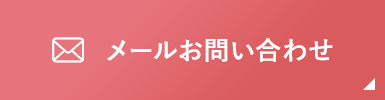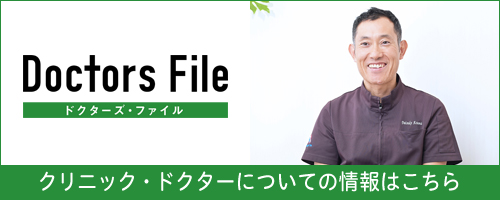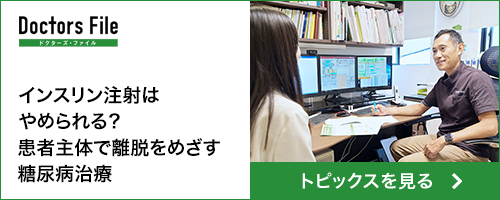治療実績更新のお知らせ
2015年8月の開院から2025年11月までに208名の患者様がインスリン離脱を達成しています。
2型糖尿病の患者さんであればインスリンはいつかやめることができるという信念で診療しておりますが、主治医だけでなく患者さんも同じ思いで日々努力されている結果だと思います。
最小限の努力で最大限の結果が出るべく、これからもよろしくお願いいたします。
12月6日 かかりつけ医で高める血糖コントロールの質~合併症を防ぐ診療戦略~
2025年12月6日に「臨床試験と使用経験から見えてきた当院でのGLP-1製剤のポジショニングの変化について~当院でのマンジャロ350例の臨床的検討を踏まえて~」の名目にて医療法人ロングウッド北千里前田クリニック院長 前田 和久 先生に講演をいただきました。
ーーーーー
2025年11月27日
かかりつけ医で高める血糖コントロールの質~合併症を防ぐ診療戦略~
講演:「臨床試験と使用経験から見えてきた当院でのGLP-1製剤のポジショニングの変化について~当院でのマンジャロ350例の臨床的検討を踏まえて~」
座長:医療法人ロングウッド北千里前田クリニック院長 前田 和久 先生
ーーーーー
11月27日 GIP/GLP-1 RA WEB seminar in 阪神北
2025年11月27日に「臨床試験と使用経験から見えてきた当院でのGLP-1製剤のポジショニングの変化について~当院でのチルゼパチド350例の臨床的検討を踏まえて~」の名目にてたわらもと内科糖尿病内科 院長 俵本 和仁 先生に講演をいただきました。
ーーーーー
2025年11月27日
GIP/GLP-1 RA WEB seminar in 阪神北
講演:「臨床試験と使用経験から見えてきた当院でのGLP-1製剤のポジショニングの変化について~当院でのチルゼパチド350例の臨床的検討を踏まえて~」
座長:たわらもと内科糖尿病内科 院長 俵本 和仁 先生
ーーーーー
11月6日 第27回 阪神糖尿病セミナー(HANDS)
2025年11月6日に「インスリンからの離脱を目指したチーム医療の取り組み」で当院看護師 嶋田が講演させていただだきました。
ーーーーー
11月6日 第27回 阪神糖尿病セミナー(HANDS)
講演 インスリンからの離脱を目指したチーム医療の取り組み」
講師 看護師 嶋田
開院以来200名を超えるインスリン離脱に成功した患者さんの背景や、開始時の思い、離脱ポイント、インスリン施行時の苦労などのアンケート結果をスタッフ皆でまとめて講演させていただきました。
以下は講演内容の抜粋です。
糖尿病を長期間患い、20年にわたりインスリン注射を行っていた患者様でも離脱を達成された方がいらっしゃいます。
ご本人の努力のみならず、ご家族の支援や医療スタッフによる包括的サポート(チーム医療)を通じて治療を進めることで、インスリン離脱が可能となります。
これからも当院に通院されている患者さんの気持ちの良き理解者となり、治療や生活の自立を支える援助者になれるよう精進してまいります。
ーーーーー
10月9日 GIP/GLP-1 RA WEB seminar
10月9日に「マンジャロ上市に伴った当院でのGLP-1製剤のポジショニングの変化~350例の臨床的検討~」で講演させていただだきました。
ーーーー
10月9日 GIP/GLP-1 RA WEB seminar
講演 マンジャロ上市に伴った当院でのGLP-1製剤のポジショニングの変化
~350例の臨床的検討~
座長: 芦田内科 院長 蘆田 延之先生
ーーーー
当院のマンジャロ実績について
本年6月よりマンジャロ関連にて多数の講演依頼を頂いております。当院での処方実績も350例を超えてきました。
マンジャロを治療早期に導入することで速やかに血糖体重が改善することも多々経験しますが、
インスリン併用の難治症例の患者さんがマンジャロ開始することで血糖が改善しインスリンが離脱した症例も多数経験しております。
毎月、当院のHbA1cの分布図を公表しておりますが、8%以上の患者さんが2022年7月の時点で94.7%だったのが
2025年7月時点で97.0%と改善しているのもマンジャロの影響が寄与していると考えております。
引き続き当院のデータをもとに多くの先生方、医療スタッフの皆様にも発信していければと考えております。
2025年6月以降の講演
1. GIP/GLP-1 RA 最新治療戦略セミナー
2025年6月25日(水)
講演:「マンジャロ上市に伴った当院でのGLP-1製剤のポジショニングの変化
~250例の臨床的検討~」
座長:小谷 圭 先生 ごとう糖尿病内科クリニック 顧問
2. GIP/GLP-1 RA Conference
2025年7月9日(水)
講演:「マンジャロ上市に伴った当院でのGLP-1製剤のポジショニングの変化
~250例の臨床的検討~」
座長:田守 義和 先生
兵庫県立加古川医療センター 生活習慣病センター センター長 糖尿病・内分泌内科 部長
3. マンジャロWebセミナー
2025年7月14日(月)
講演:「マンジャロ上市に伴った当院でのGLP-1製剤のポジショニングの変化
~250例の臨床的検討~」
座長:合屋 佳世子 先生 西宮市立中央病院 糖尿病・内分泌内科部長/糖尿病センター長
4. 明日からの糖尿病治療を考える会
2025年8月25日(月)
講演:「マンジャロ上市に伴った当院でのGLP-1製剤のポジショニングの変化
~250例の臨床的検討~」
座長:李 英子 先生 尼崎医療生協病院 内科
5. GIP/GLP-1 RA seminar ~明日からの糖尿病治療を考える会~
2025年9月3日(水)
講演:「マンジャロ上市に伴った当院でのGLP-1製剤のポジショニングの変化
~300例の臨床的検討~」
座長:今井 暖 先生 明石市立市民病院 糖尿病内科 副医長
6. GIP/GLP-1 RA Seminar in Oita
2025年9月11日(木)
講演:「GIP/GLP-1製剤上市に伴った当院でのGLP-1製剤のポジショニングの変化
~300例の臨床的検討~」
座長:日髙 周次 先生 大分県厚生連鶴見病院 糖尿病・代謝内科 部長
5月29日(水)ケレンディア錠Luncheon Seminarにて
「糖尿病性腎症進行抑制を主眼に置いた当院での治療の実際」で講演させていただだきました。
透析導入の原因の第一位は糖尿病であり、糖尿病性腎症の診断基準にアルブミン尿測定が含まれておりますが糖尿病専門医であっても十分に測定されているとはいえません。
当院では2015年の開院時より院内で測定できるようシステムを組んでおります。アルブミン尿測定の意義と腎症抑制の当院での実績をもとに講演させていただきました。
7月8日(土)第25回阪神糖尿病談話会にて
「28年と長期インスリン患者を通院後6年で離脱に導きその後も良好な血糖管理を維持できている1例」という演題で発表いたしました。
この方は長期にインスリン療法(最大25単位/日)を施行されておりましたが、ご本人の努力もありインスリン離脱を達成されたのみならず体重も15㎏程減量され、合併症の進展も抑制されていることもあり発表させていただきました。
出席いただいた先生方からも多数質問をいただき活発な議論をさせていただきました。
4月27日(水)糖尿病Web Live Seminar 2022
4月27日に 糖尿病Web Live Seminar 2022にて「構造化されたSMBG測定で行動変容を促す糖尿病治療」という演題で講演させていただきました。
672名と多くのコメディカルの方々に視聴いただきました。
・インスリン離脱を前提に患者さんが主体となって単位数を調整していく治療方針が印象にのこりました。(看護師)
・SMBGの測定や平均値、標準偏差をみることの重要性(看護師)
・SMBG測定のアルゴリズムについて、とてもわかりやすく、栄養指導も治療方針に沿って行いやすく、治療方針を医師と共有できていきちんと理解できていると患者さんにも説明しやすい(栄養士)
・SMBGが行動変容のきっかけとなるように今後携わっていきたい(看護師)
等々 多くの感想をいただきました。実際に糖尿病診療に携わっている方でも未だにインスリン離脱について講演すると反響をいただきますが、
当院だけでなくどの施設でも当たり前になるよう微力ではありますが、今後も活動を続けてい参りたいと思いました。
低血糖なく血糖変動の正常化を目指す当院での治療法 ~クラウド連携とSMBGの活用法~
3月17日に「低血糖なく血糖変動の正常化を目指す当院での治療法~クラウド連携とSMBGの活用法~」という演題名でWEBにて講演させていただきました。
良好な血糖管理を達成するためには、指先で患者さんご自身が食前と食後2時間の血糖値を測定し、血糖の流れを自己評価することが重要と考えております。
当院での取り組みについて講演させていただきました。
合併症進展抑制を意識したGLP-1製剤の選択
11月18日に「合併症進展抑制を意識したGLP-1製剤の選択」という演題名でWEBにて講演させていただきました。
当院では、糖尿病性腎症の指標になるアルブミン尿を院内にて測定可能で定期的に検査を行っていますが、GLP-1製剤を使用することで多くの方がアルブミン尿が改善されています。
GLP-1製剤のみならず血糖変動幅を小さくすることが合併症抑制につながる点を強調して講演させていただきました。
第57回 糖尿病学会近畿地方会
糖尿病学会近畿地方会にて「頻回Ins患者をBOTに変更後、Self Titrationを用い緩徐にInsを減量、離脱に導いた1例」という演題名で発表させていただきました。
開院以来のインスリン離脱患者総数が120名となり、離脱された方の背景(罹病期間やインスリン治療期間など)も提示しました。定期的なSMBG(自己血糖測定)の実施を徹底することで長期インスリン患者でも離脱は可能であることと共に特徴的症例を1例提示しております。
奇しくもこの症例はべんちのーとで取材させていただいた患者さんとなります。取材当時はインスリンを継続されておりましたが、取材当時の目標が達成され僕も大変うれしく思っています。
記事も含めてご参照いただければ幸いです。
インスリン離脱患者数の検討ページを公開しました
2015年8月の開院以来、毎月のHbA1c 1,5-AGの結果と共にインスリン離脱者数を公開してまいりました。
患者さん個々の努力もあり大変うれしいことに離脱総数が100名を突破いたしました。
離脱を達成された方の背景(罹病期間やインスリン離脱までの期間)、離脱継続率などをまとめてみましたので是非ご覧ください。
また、離脱された方のアンケート結果も一部掲載しています。今現在インスリン治療をされている方にとっても大変参考になるご意見だと思います。ご参照頂ければ幸いです。
ただ、誰もがインスリン離脱が好ましいわけではなく、少量のインスリンが良好な血糖管理に必要な方もいらっしゃいます。しっかりとインスリンの適応を見極め、必要最小限の薬剤使用を医師も患者さんも心掛けることが重要だと思います。
詳しくはこちら
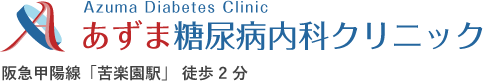
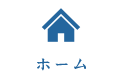

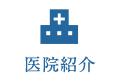


 当院でカード決済が出来るようになりました。
当院でカード決済が出来るようになりました。